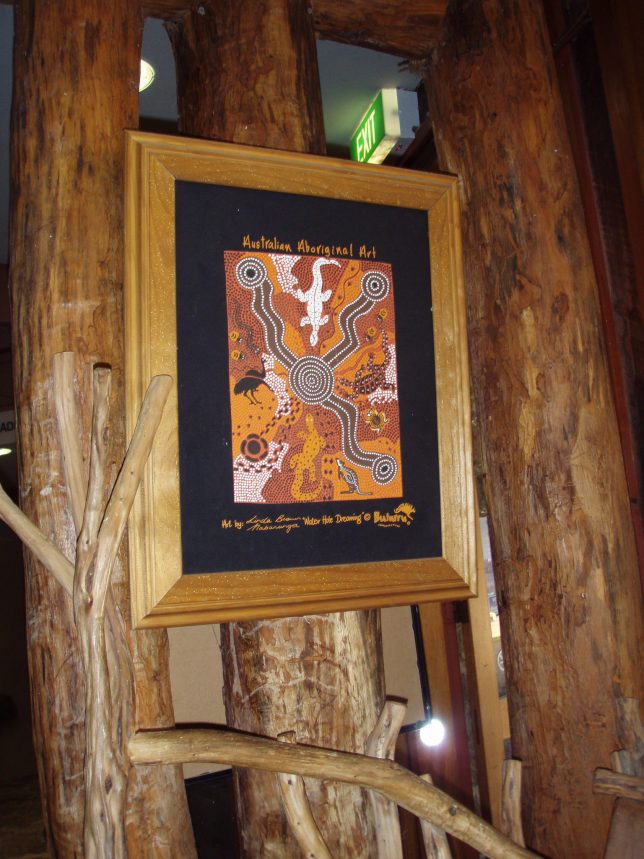一人歩きする言葉たち
毎日、Facebookを開いて、あるグループの投稿を読んでいます。参加者が1000人を超えるにも関わらず、非公開設定なので、かなり白熱した議論も起こります。参加条件があって、日常生活において、多少の違いはあれど、同じ信条を持っている人たちなのです。それでも、世の中の縮図が言葉から観察できるので、面白いものだな、と感じています。その中には、様々な人がいるのですが、議論に参加するのは、決まっている人ばかりで、50人未満です。非常に知的な言葉使いをなさるので、とても勉強になるのですが、時折、どう考えてもお互いが言いたいことを言っているだけじゃないかな?という事もあります。それで議論が成立しているのかは疑問ですが、その後もやり取りが続くのです。平行線を歩いている、と表現されるのが一般的かもしれませんが、まさに、その通りだと言えます。それでもお互いが納得できているのであれば良いのではないか、とは思います。「言葉」は伝わっても「真意」は伝わりにくいものなのだな、とは常々思いますが、それは自分の表現が悪いからだ、と考えていました。しかし、他のやり取りを見ていると「ああ、自分だけではないのだな」と少し安心します。そういった時に、翻意を伝える第三者が存在したら、それほど拗れることは無いのでしょうけれど、そんなに都合よくはいません。インターネットという特性も相まって、感情に沿って言葉だけが一人歩きして、相手が存在していることを忘れがちになってしまうのでしょう。言葉って便利ですが、あくまでも表層的な部分でしかなく、その真意はニーチェが言ったように「事実など存在しない。解釈があるのみ」なのです。つまり、同じ言葉を発しても人それぞれの受け止め方が異なるということですね。これをIT用語ではポリモーフィズム(多態性・多様性)と言いますが、これは前に書きました。ではこのブログは何が言いたいのか、と思われるかもしれませんが、特に言いたいことは無くて、ただ思った事を綴っているだけです。ですから、存在価値としては全くと言っていいほどありませんが、レンタルサーバーにお金を払っているので、その分は何とか消費しなければ、と損得勘定丸出しの動機です。それでも続いているので、まあ自分でも驚いています。書いていることのほとんどは繰り返しであり、新しい考えを毎日書くことはありません。ただ、考え方が変化しています。つまり、矛盾した発言をしている、ということもありますが、それは「成長」と捉えています。人生の折り返し地点だからといって、精神的にまで折り返す必要はありません。常に時が進むように、成長も続けたいものです。